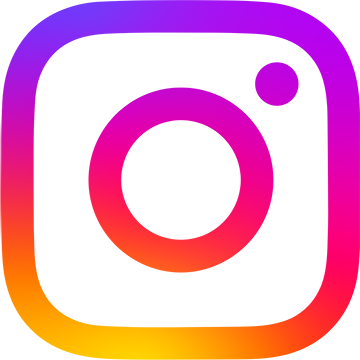妙高市SDGs普及啓発実行委員会では、未来の地球環境と地域のあり方について考える機会として「おだやかな革命」上映会を開催しました。生活と自然、そして、私たちの日常がつながる物語を通じて、次世代に引き継ぐ暮らしの形を考えました。
妙高市SDGs普及啓発実行委員会では、セミナーや映画上映等の体験を通じ、SDGsの普及に努めています。次回も皆様のご参加をお待ちしております。
●「おだやかな革命」(予告編)
(ご注意)動画を再生すると音声が流れます。ご注意ください。
概要・あらすじ
【概要】
自然と向き合い、人と向き合い、地域と向き合いながら、これからの暮らしを自らの手で作り、本当の豊かさを取り戻していく地域の姿を追ったのは、前作「よみがえりのレシピ」で、伝統野菜のタネをめぐる物語を描いた渡辺智史監督。「暮らしの選択」、その先にある、「幸せな社会」に向けての取り組みが各地で始まっている。ナレーションを女優の鶴田真由が務める。
【あらすじ】
原発事故後に福島県の酒蔵の当主が立ち上げた会津電力。放射能汚染によって居住制限区域となった飯館村で畜産農家が立ち上げた飯館電力。岐阜県郡上市の石徹白、集落の存続のために100世帯全戸が出資をした小水力事業。さらに、首都圏の消費者と地方の農家、食品加工業者が連携して進めている秋田県のにかほ市の市民風車。自主自立を目指し、森林資源を生かしたビジネスを立ち上げる岡山県西粟倉村の取り組み。都市生活者、地方への移住者、被災者、それぞれの「暮らしの選択」の先には、お金やモノだけでない、生きがい、喜びに満ちた暮らしの風景が広がっていた。成長・拡大を求め続けてきた現代社会が見失った、これからの時代の「豊かさ」を静かに問いかける物語。
※映画「おだやかな革命」公式ホームページより引用
上映会参加者の感想
参加された方々からの感想を一部ご紹介いたします。自分たちの生活を見直すきっかけになったり、環境とのかかわりかたを考えるきっかけとなったりしたようでした。中には、太陽光発電のように省エネとされるものでも、廃棄される際の資源消費などの視点も考える一助になったようです。
ちなみに、ある製品の原材料調達から使用、廃棄されるまでのライフサイクル全体をとおしてCO2をはじめとする温室効果ガスの排出量や、環境への負荷を算定する手法を「ライフサイクルアセスメント(LCA)」と呼びます。私たちが、脱炭素を目指すうえで大切な視点になります。
- ・内容に興味があって来たが、観に来てよかった
- ・地球の将来を見据えたとき、まさに自然を大切に持続可能なシステムを改めて考える機会になりました
- ・地域がその地域らしく、存続していくことの大切さを学びました。とてもよかったです
- ・やはり実際に目にすることができてよい経験になりました。素敵な取組がたくさん紹介されとてもよかったです
- ・太陽光発電は本当に持続可能なのか。壊れてしまったら廃棄のコストはどう計算しているのか疑問に感じた
- ・様々な形の地域づくりがでてきてよかった
- ・「木や水、土」といった資源は改めて大切だと思った
- ・地域循環型の生活をしていきたい
- ・原点に返り、生活を見直したいと思った。まずは家庭菜園を充実させて自給力を高めてみようと思う
- ・食べ物を無駄にしない。衣服などは最後まで無駄にせず消費する。作れるものは買わない。土に戻るものは肥料化するなど心がけたい